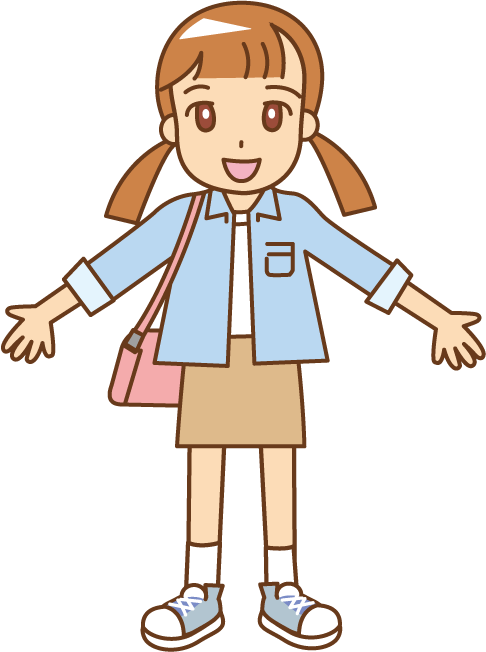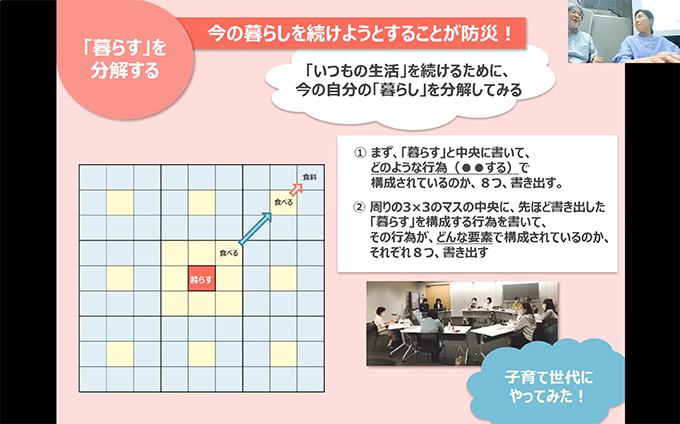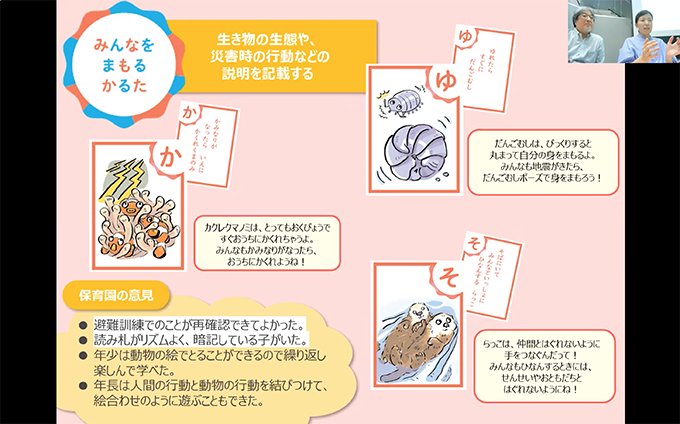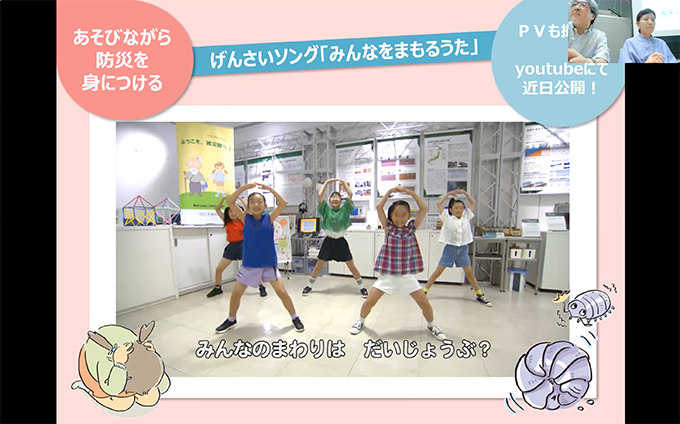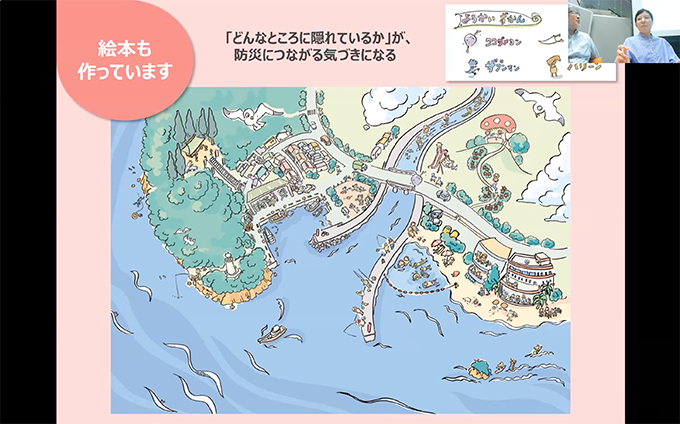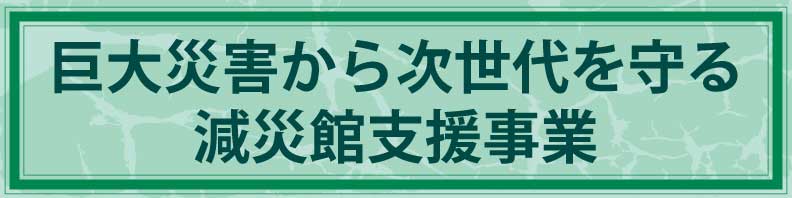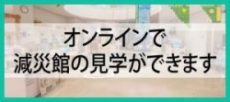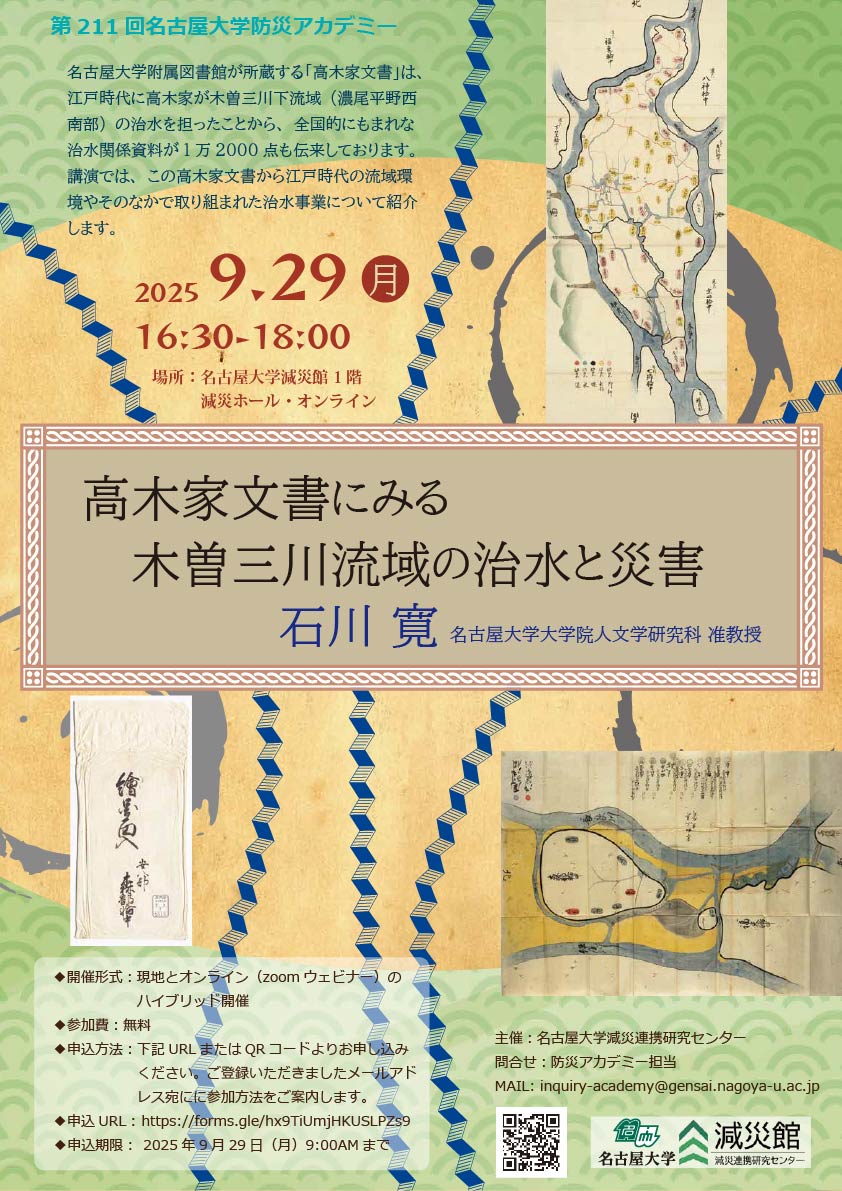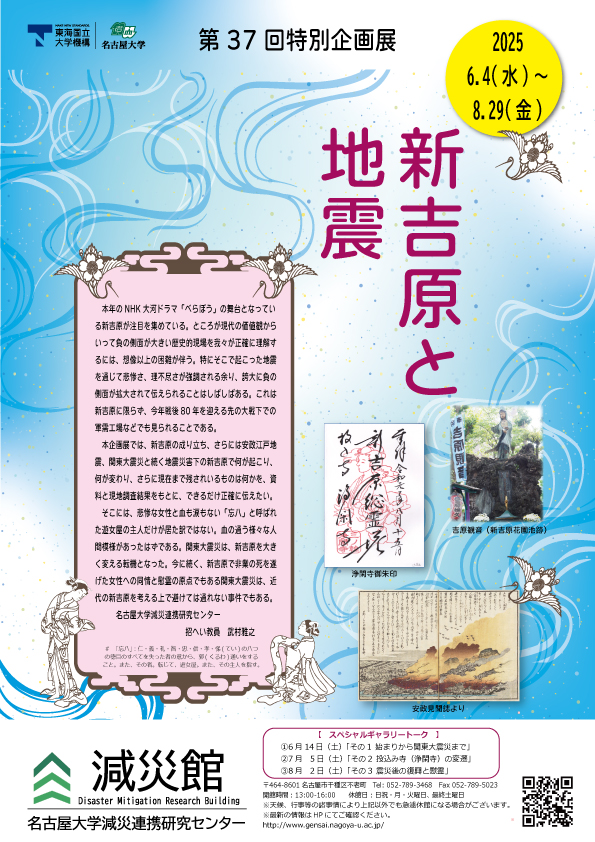63年前のきょう起こったこと~伊勢湾台風の高潮被害をいまの減災にどう生かすか~
ゲスト:防災工学者 富田 孝史 さん
(名古屋大学減災連携研究センター教授)
日時:2022年9月26日(月)18:00~19:30
場所:名古屋大学減災館1階減災ギャラリー・オンライン
企画・ファシリテータ: 隈本 邦彦 さん
(江戸川大学教授/名古屋大学減災連携研究センター客員教授)

伊勢湾台風をテーマにした今回のカフェは、2022年9月26日午後6時からの開催としました。
伊勢湾台風は、そのちょうど63年前、1959年9月26日の午後6時過ぎに紀伊半島に上陸しましたので、ちょうど同じ日の同じ時間にげんさいカフェを開いて、改めてあの台風がどんな台風だったのか、その経験を今後の防災に役立てることができないか、ということで研究者と市民との対話を試みました。
土木の分野で高潮や津波の対策に詳しい富田孝史さんにゲストに来ていただきました。
最初に、名古屋市が制作した伊勢湾台風の記録映画を見て、死者行方不明者5000人を超えるその被害を、参加者の皆さんにもう一度思い出していただきました。この日が身内の命日という方も多数いらっしゃいますので、改めて皆さんのご冥福をお祈りしました。
富田さんからは、伊勢湾台風がどれくらいすごい台風だったのかというデータの説明をいただきました。
上陸した時点での中心気圧が929.5ヘクトパスカル。これは上陸時の勢力としては、我が国の観測史上4番目に強い台風です。そして名古屋にとっては、63年前のこの日に観測された最低気圧958.2ヘクトパスカルが、いまだに観測史上最低の気圧なのだそうです。そして10分平均の最大風速37.0メートルと最大瞬間風速45.7メートルというのも観測史上最大の記録で、これらの記録は63年間破られていないのだそうです。
伊勢湾台風は紀伊半島付近を北上しましたが、この進路は、ちょうど伊勢湾の奥の方向に向かって風が強くなるコースでした。台風の東側では台風の進路と風向きが同じ方向になるため風が強くなりがちだからです。この暴風によって海の水が吹き寄せられる効果に、気圧の低下による吸い上げ効果が加わって、名古屋港では、標高3.98メートルの高さまで海面があがりました。高潮は名古屋港の貯木場を襲い、大きな丸太が大量に流されたことにより、被害がさらに拡大したと言われています。
富田さんから、その夜、名古屋港の海面がどのように変化したかというグラフを見せていただいて、一つ大きな発見がありました。
それは、実は最も高潮が高くなったのは26日の夜9時35分ごろですが、名古屋港の満潮時刻は翌27日の午前0時前後だったということ。つまり最高潮位は、この日の満潮よりだいぶ前にやってきたということです。
つまり、これくらいの台風による高潮となると、潮の満ち引きとは変化のレベルが違うということでもあります。
もちろん満潮と台風による高潮が重なると危険だ、ということは言えますが、逆に“満潮になるまでは安心”と思ってはいけないということです。満潮時刻は分単位で決まっていますから、ニュースなどでは、それが台風情報とともに発表されます。あくまでこれは参考であって「満潮はだいぶ先だから」と港の様子を見に行ったりしてはいけないということですね。


あと、今回のカフェで富田さんが強調したのは、、実は高潮が起きるかどうかは、台風の勢力=中心気圧だけではなく、通過コースが大きな要素だということです。数10キロ、コースがずれるだけで起きたり起きなかったりします。
上述のとおり、伊勢湾台風は名古屋にとって最悪のコースを通ったわけですが、例えば、関西空港の橋に大きな船が衝突した風台風の2018年8月の台風21号の場合、上陸5日前の時点の台風の予報円の中心は、伊勢湾台風とほぼ同じコースだったということで、何しろ非常に強い勢力ですから、名古屋の防災関係者は相当身構えていたのだそうです。
実際には予想進路が、少しずつ西に修正されていって、最終的には徳島県から淡路島のあたりを通過しましたので、大阪はたいへんな被害になりましたが、伊勢湾台風の再来ということにはなりませんでした。どのようなコースを進むかは高潮対策では重要な要素なのですね。
教訓になるのは、伊勢湾台風の6年前の1953年(昭和28年)9月に、死者500人近くが出た台風13号が東海地方を襲いましたが、この時、高潮の被害が大きかった愛知県の碧南、美浜、武豊、内海といった自治体では、その経験を生かして、伊勢湾台風の時にはすばやく避難命令が出て、犠牲者があまり出なかったということです。
また台風13号で被害を受けたところの復旧工事では、堤防が海側だけがコンクリートの「一面張り」ではなく、堤防の上と陸側もコンクリートになっている「三面張り」になっていてこれもこれらの地域の被害が少なかった理由と考えられていているそうです。
他にもカフェではこんなお話もありました。
伊勢湾台風が上陸した63年前の9月26日は土曜日で、当時は役所も会社も午前中で終わる半ドンでした。
ということで気象台も、防災対応に関係する多くの人が家に帰ってしまう前に説明をしておかないとと考えて、午前10時から台風予想についての説明会を開いたそうです。そして午前11時15分には暴風雨、高潮、波浪警報を出しました。
ところがその時点ではまだ名古屋は晴れていて、気象台の説明会に来た記者が「こんなにいい天気なのに、ほんとに台風来るのかよ」とぼやいていた、と気象台の記録にあるそうです。あまり早すぎる警告は考えものということなのでしょうか。
この日も会場とオンラインで180人近い方にご参加いただきました。富田さん、参加者のみなさんありがとうございました。



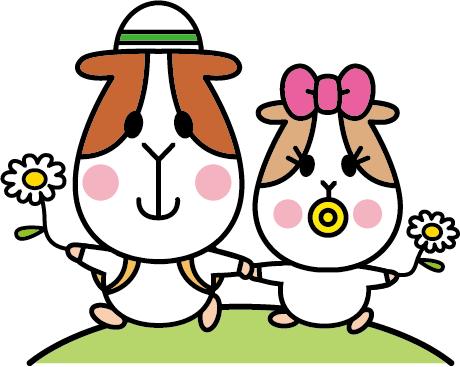
1.jpg)






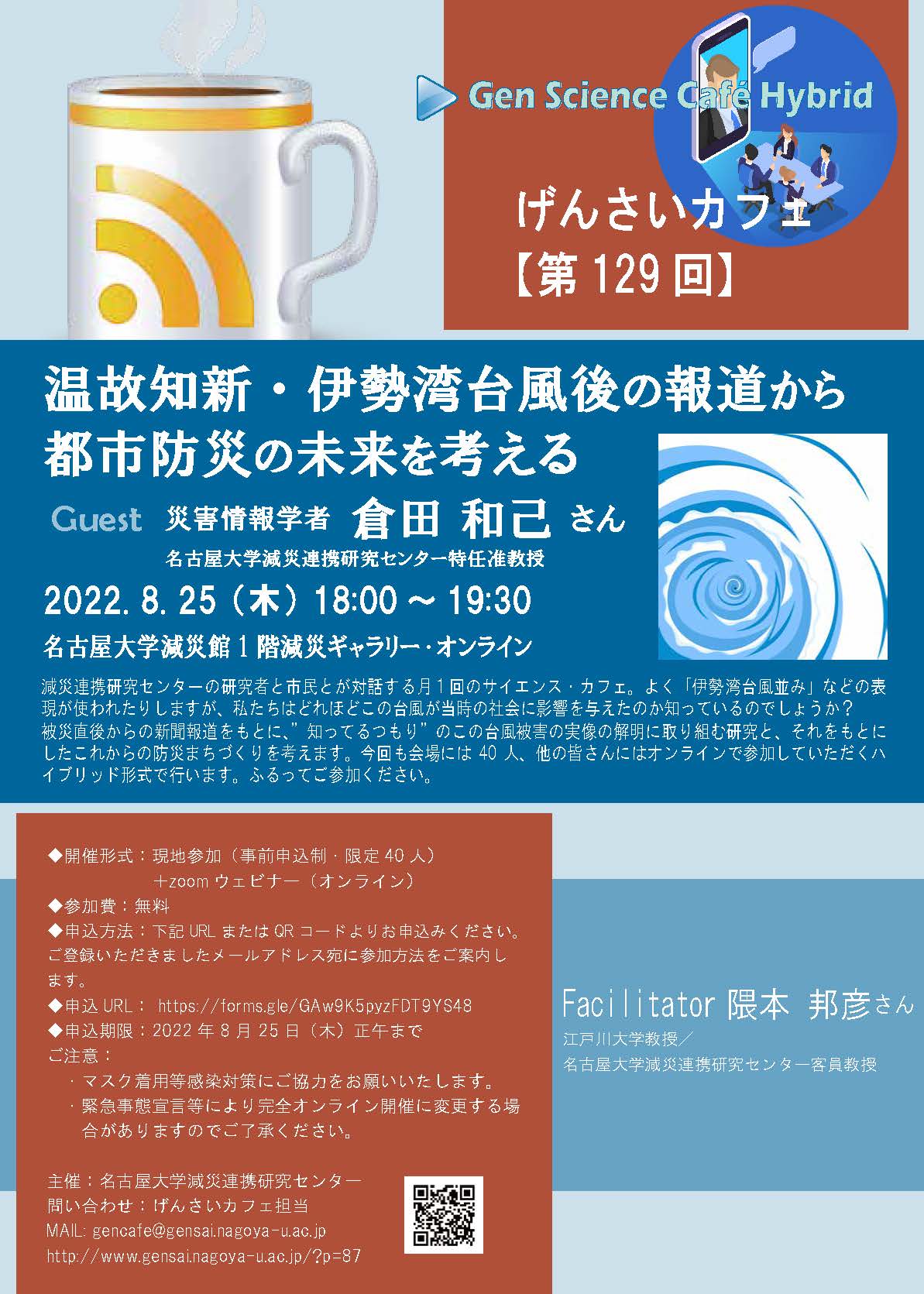
.jpg)