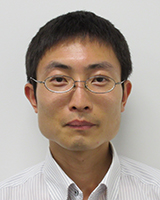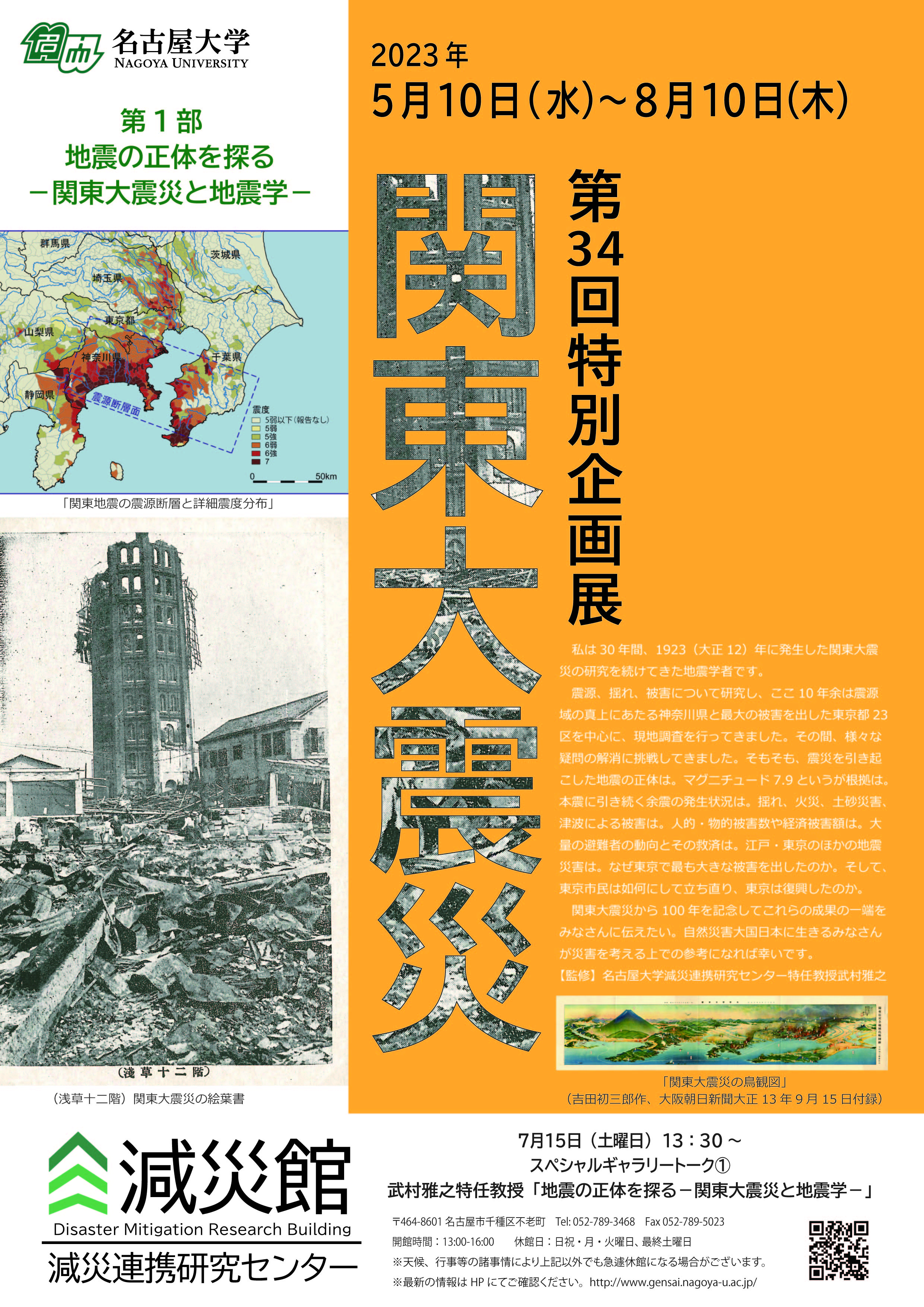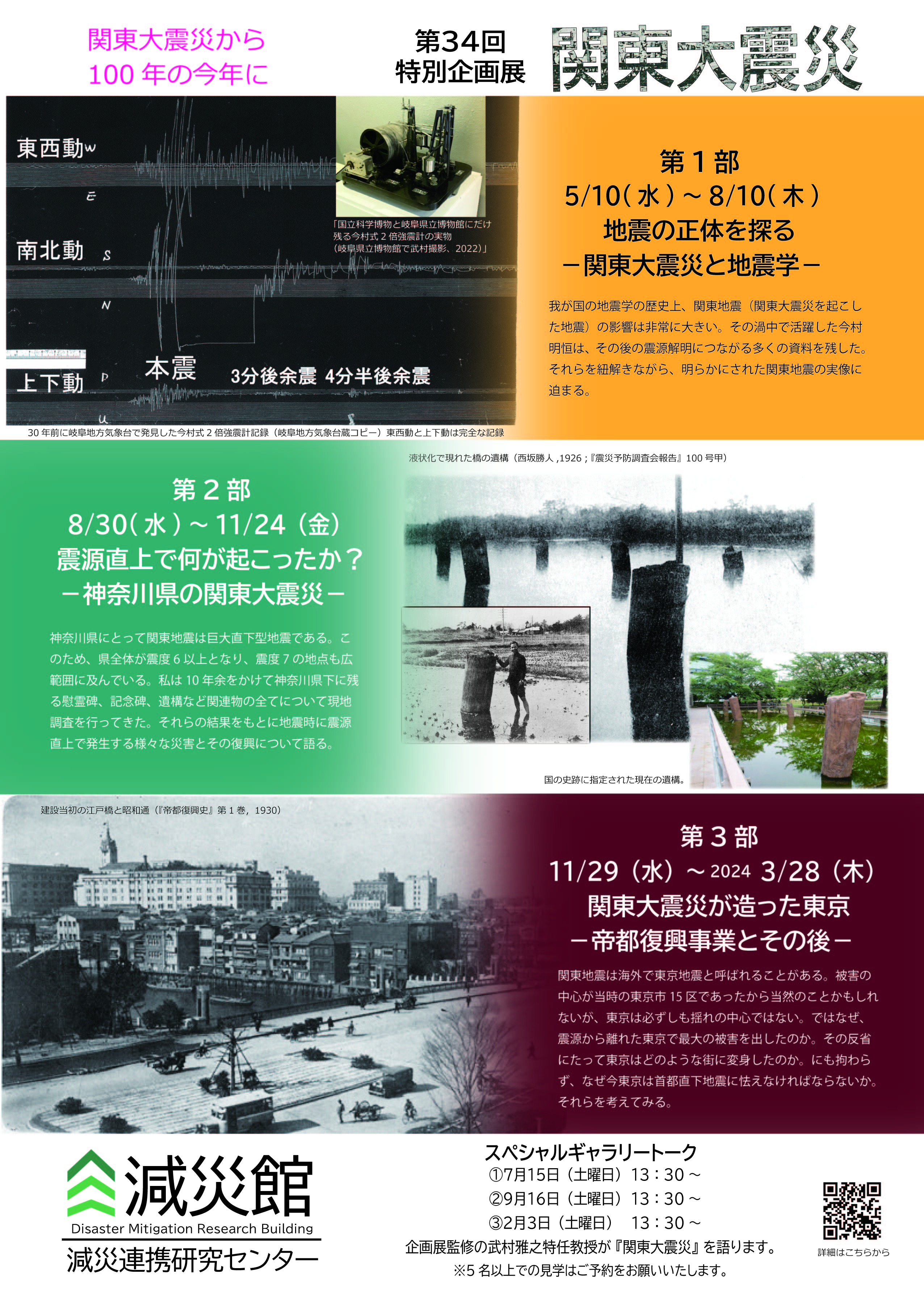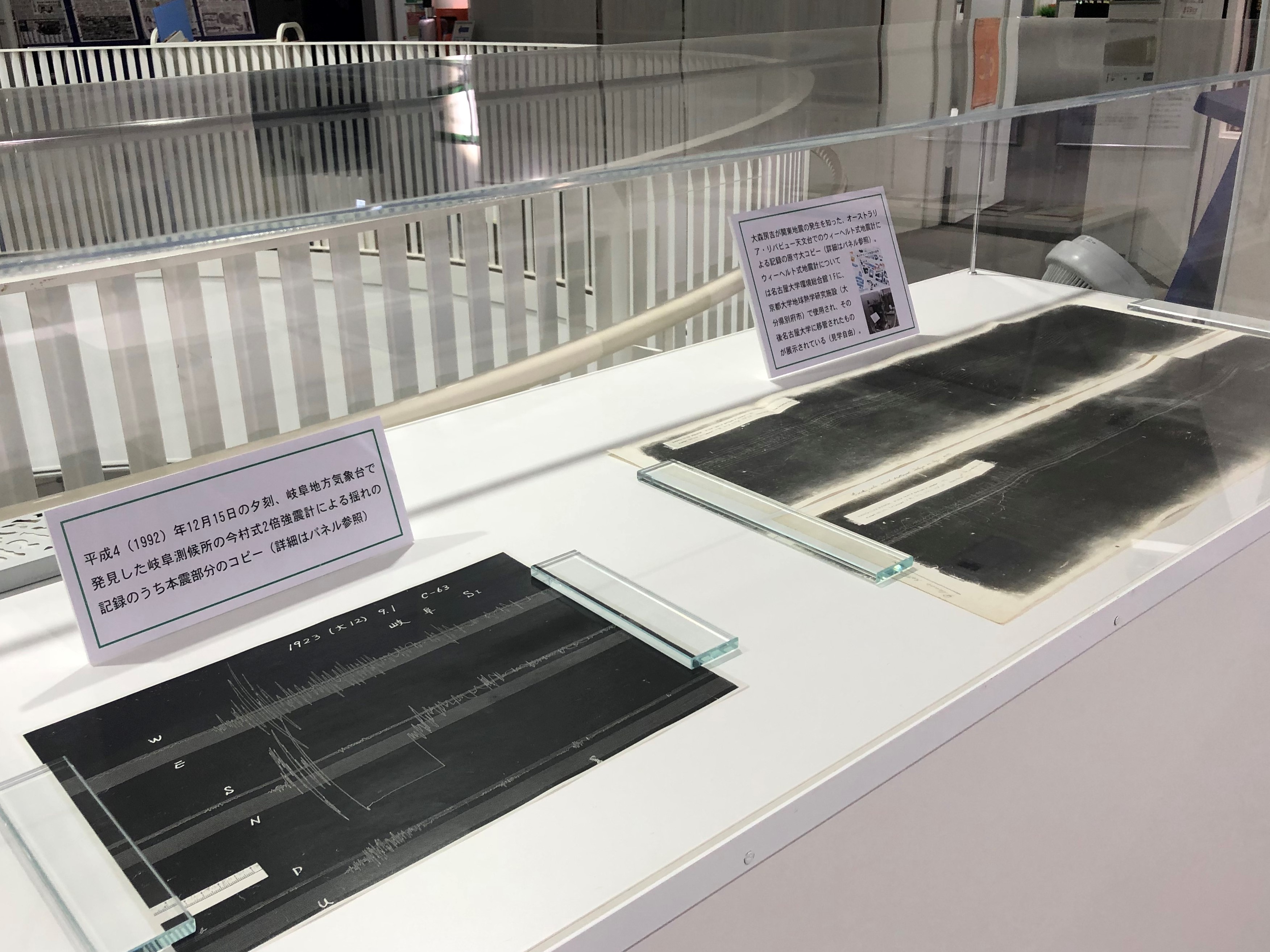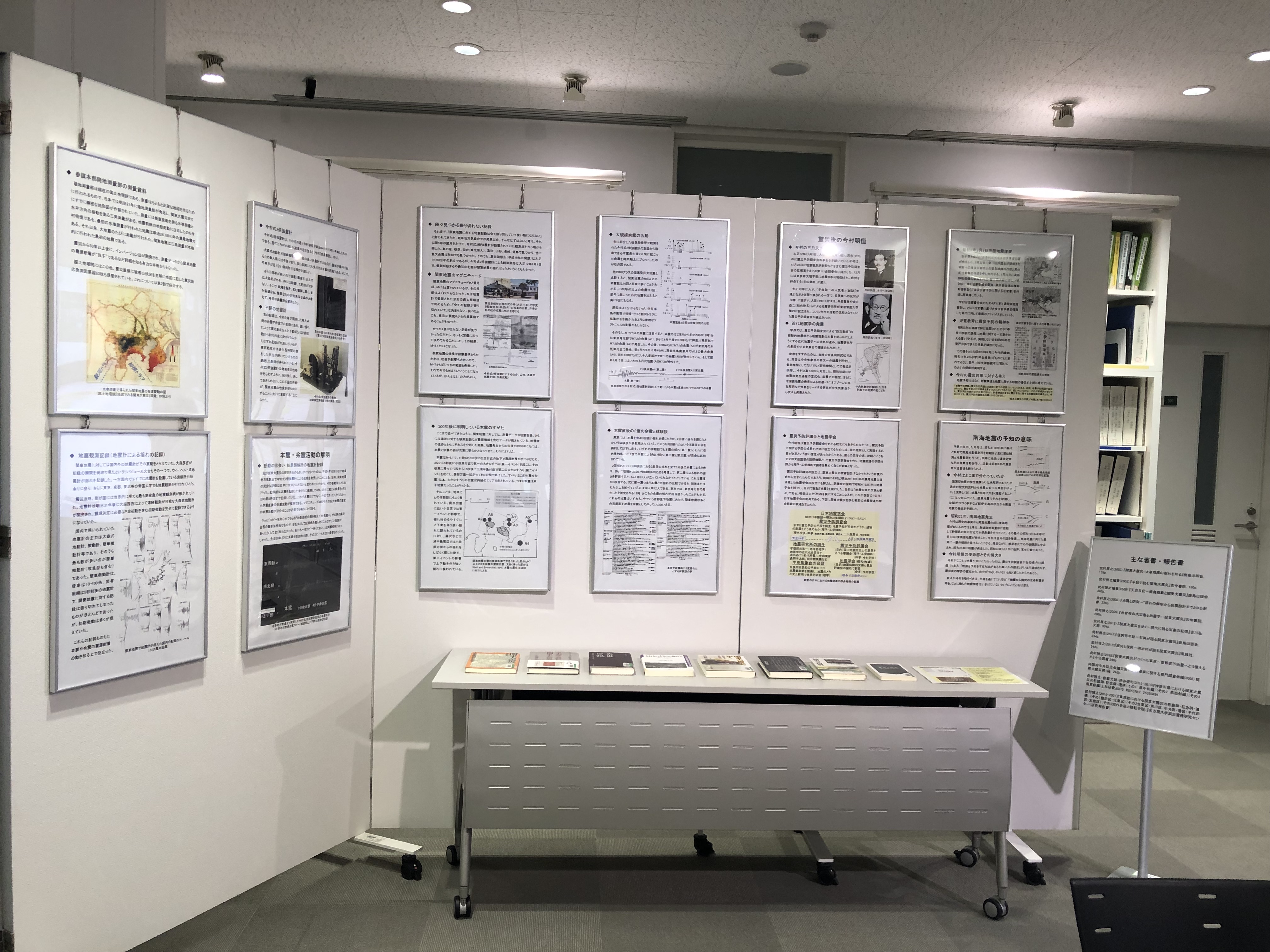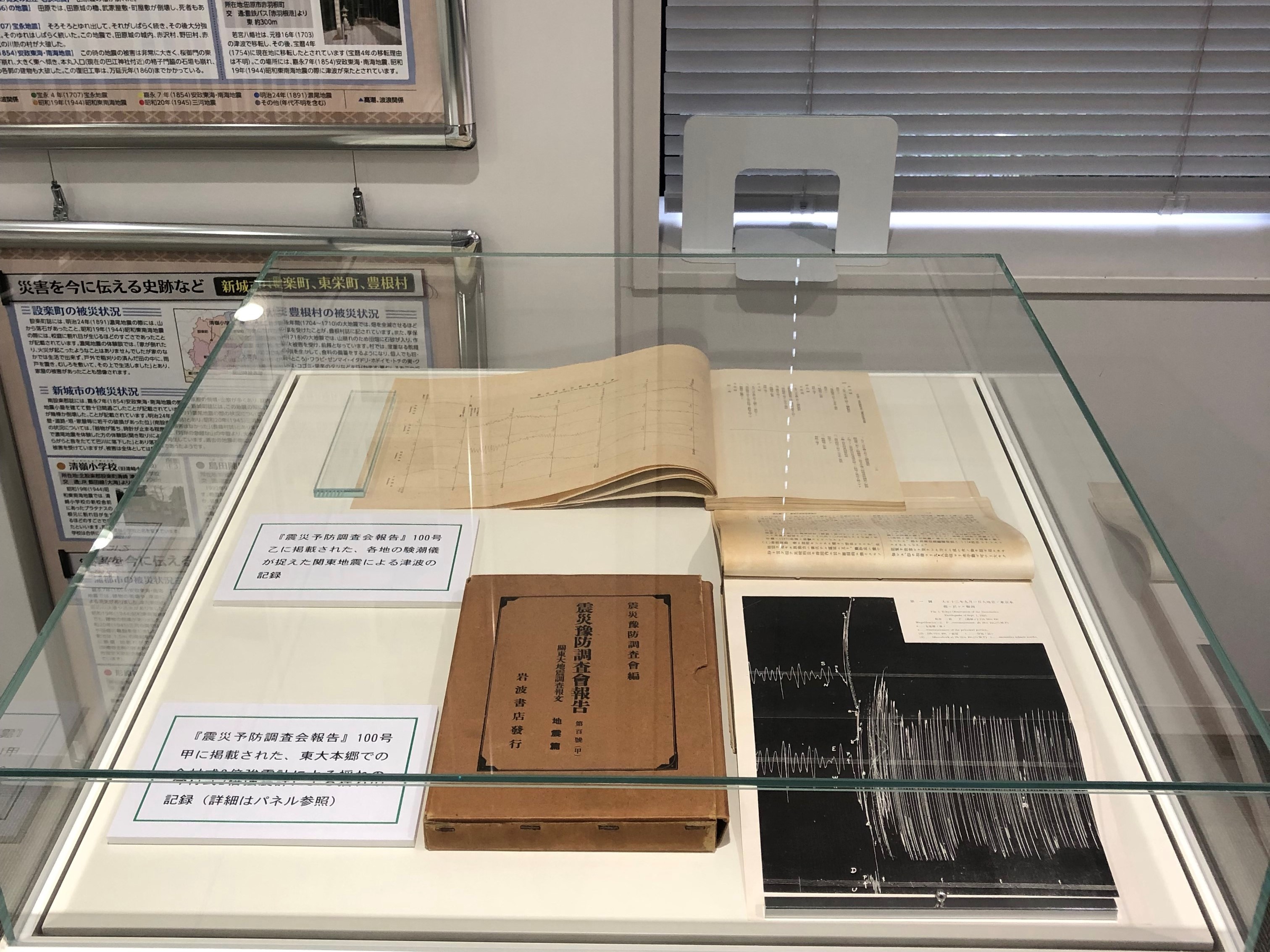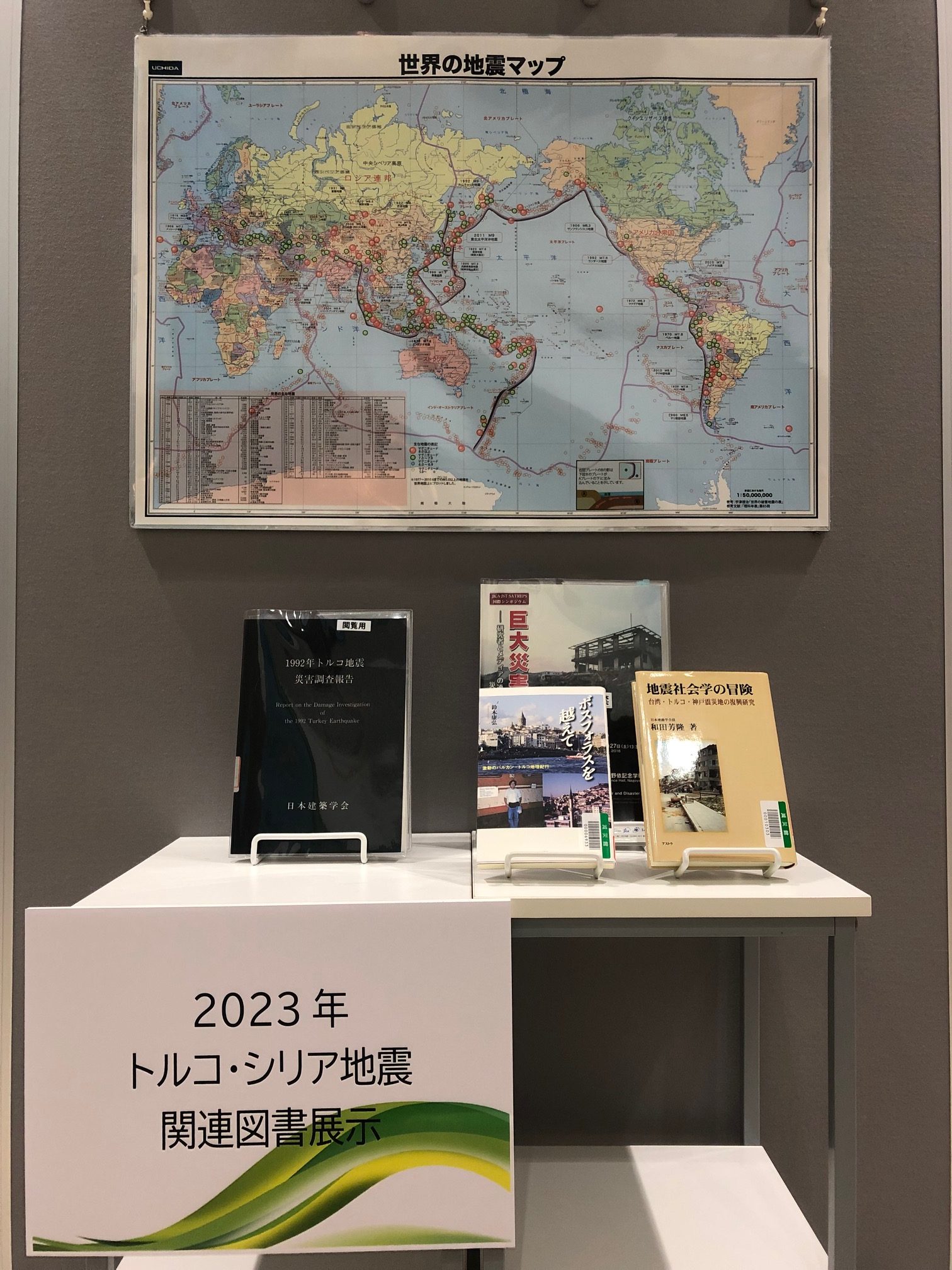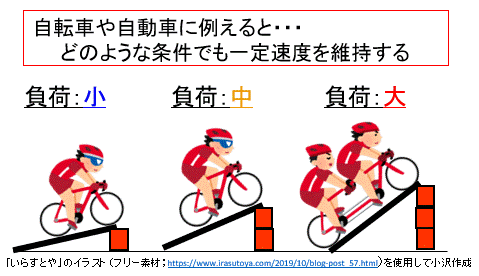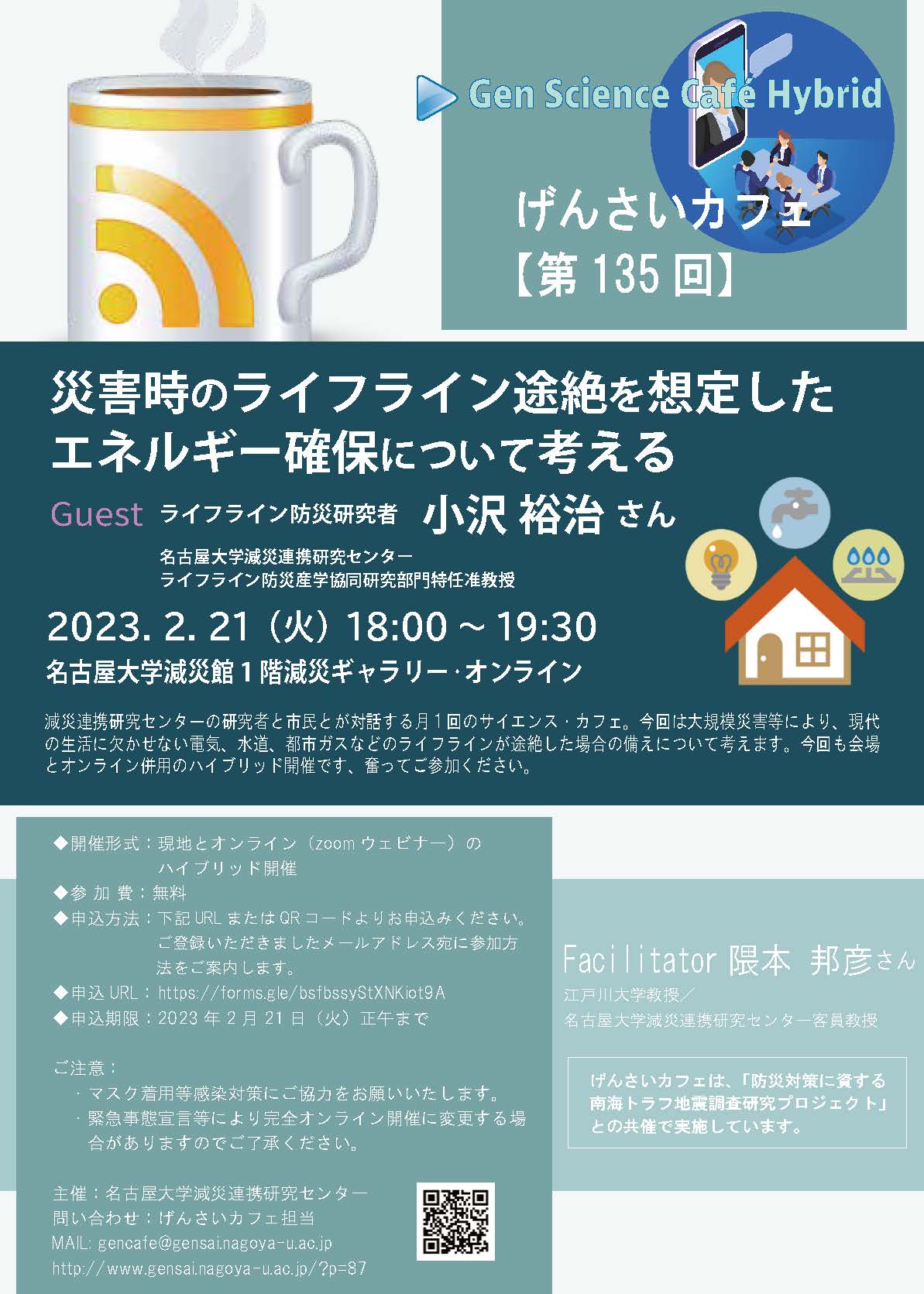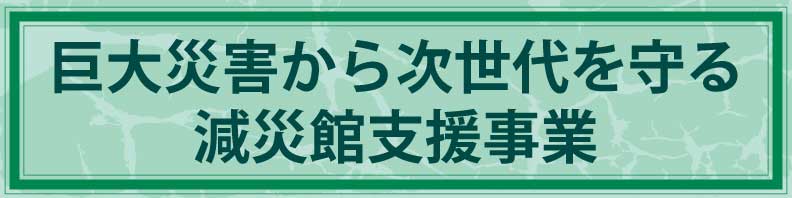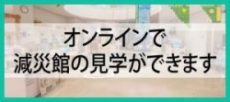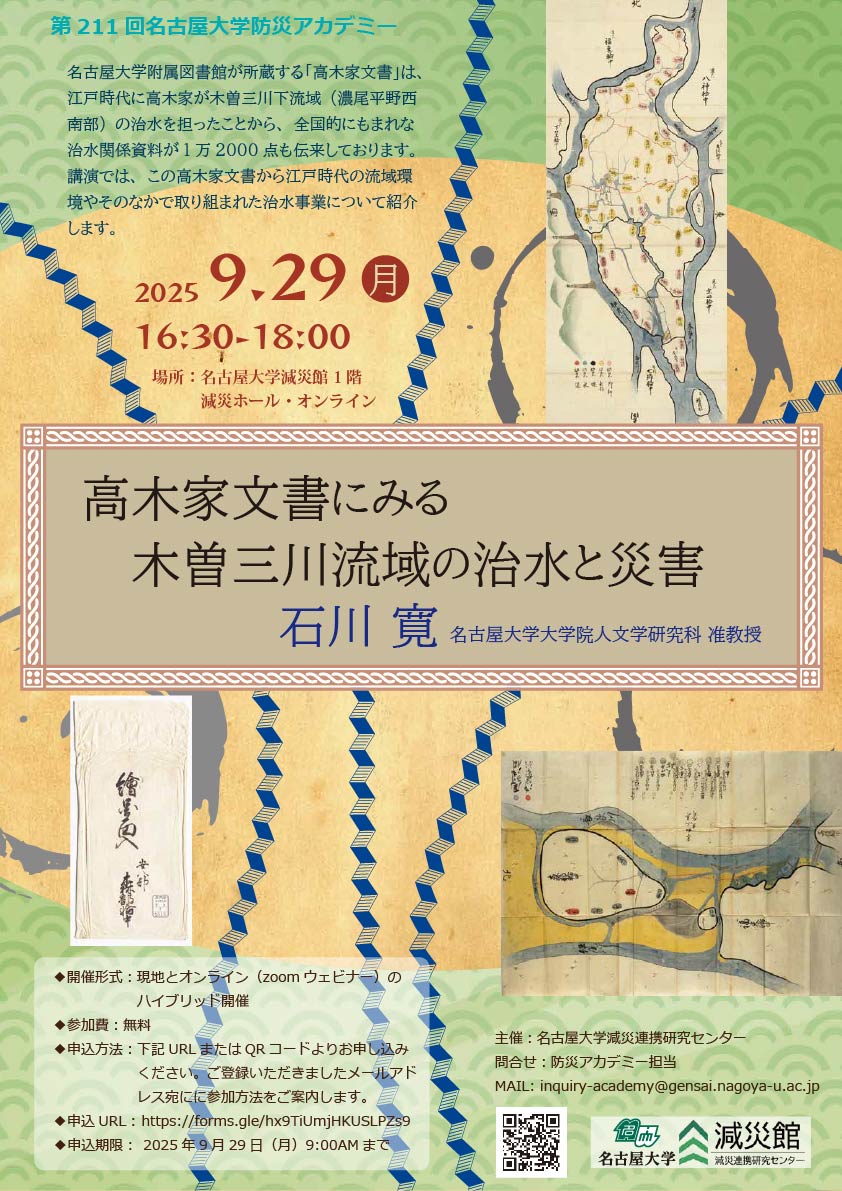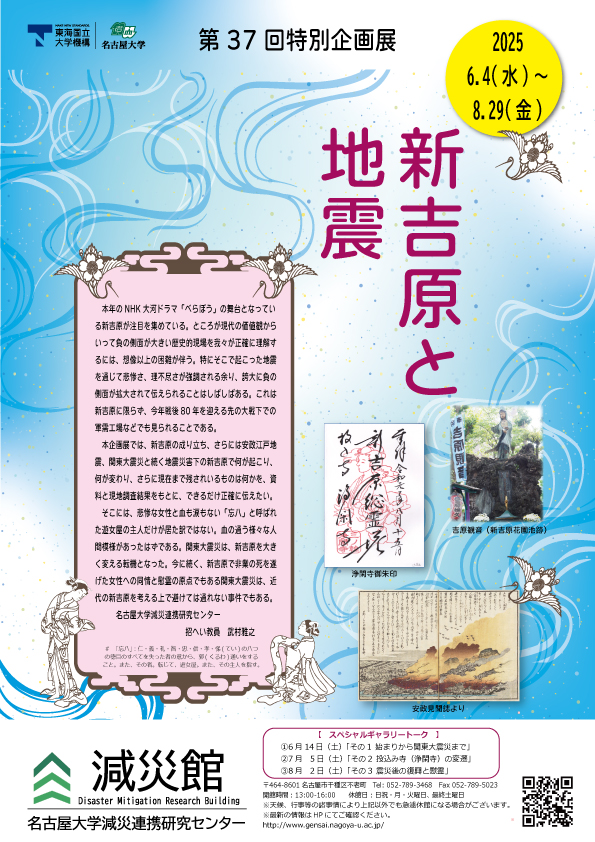異常気象って何?どう備える?
ゲスト:名古屋地方気象台長 中三川 浩 さん
日時:2023月3月22日(水)18:00~19:30
場所:名古屋大学減災館1階減災ギャラリー・オンライン
企画・ファシリテータ: 隈本 邦彦 さん
(江戸川大学教授/名古屋大学減災連携研究センター客員教授)
げんさいカフェは、「防災対策に資する南海トラフ地震調査研究プロジェクト」との共催で実施しています。

今回のゲストは、気象庁でずっと長期予報に携わり「気候リスク対策官」の経歴を持つ名古屋地方気象台長の中三川浩さんに来ていただき、よく聞く「異常気象」というのはそもそもどういう意味か、我々はどう備えればいいか、ということをテーマにしました。
異常気象とは、統計上、その季節、その場所で30年に一度くらいにしか起きない現象を言います。中三川さんによると、30年に一度というのは、だいたい人の一生のうちに1度か2度あるかないかの出来事というイメージなのだそうです。
もちろん豪雨や高温だけではなくて、逆に干ばつや冷夏なども、30年に一度くらいの頻度でしか起きないような極端な現象はみな異常気象ということになります。
地球全体の気温が上昇している今、30年に一度くらいの極端なことが結構ひんぱんに起きているような気がしますよね。でも、そうやって平年の気温や降水量も少しずつ変わっていきますから、異常気象と判断される値もまた、新しい30年の統計をもとに計算されて変化してくということです。
さて、その異常気象にどう備えるかという点で、たいへん興味深かったお話が、実は、気象庁には「異常気象分析検討会」という組織があるということでした。
もともとは気象庁の職員だけで異常気象の解析や検討をしていたそうなんですが、やはり衆知を集める必要があるということで、外部の大学や研究機関で気象を研究している先生たちにも参加してもらって「官学一体」の検討会を、定期的に、また異常気象が発生した場合には臨機に開いているそうです。委員は12人の研究者、作業部会にはさらに20人の研究者がいて、けっこう大掛かりな検討会です。
この検討会、もともとは2005年から6年にかけての「平成18年豪雪」をきっかけにして生まれたとのことでした。この年、暖冬という予想がはずれ、日本海側の各地で列車が脱線したり立往生したりするような豪雪になってしまったのですが、なぜこのような異常気象が起きたのか検討するために、このような組織が必要だということになったのだそうです。
中三川さんからは、検討会の成果の一例として、3年前の「令和2年7月豪雨」の分析についてお話いただきました。
この豪雨、東海地方でも岐阜県に大雨特別警報が出たのが記憶に新しいところですが、特に熊本県の球磨川周辺で大規模な浸水が起きました。
この時は、九州付近に「線状降水帯」が出現し、同じ地域に大雨がずっと降り続けるという現象が起りました。それがなぜあの場所で起きたのか、地球規模のデータを集めて検討会で解析したのだそうです。
その結果、実は、インド洋の海面水温が高かったことと、その影響でその東側からフィリピンにかけてのアジアモンスーンの活動が低調だったこと、それらの影響もあって、日本付近を通る偏西風の北上が平年より遅れたこと、さらには太平洋高気圧の南西への張り出しが強かったことも加わって、ちょうど日本付近の梅雨前線に向かって、西側と南側から湿った空気がたくさん流れ込んで集中する形になっていたということがわかったということです。
遠くインド洋の海面水温が、回り回って日本に大きな影響を与えていたということには驚かされました。


こうした検討会による分析が、これからの防災に役立つことが期待されています。
どういう条件の時に異常気象が起きるのか、そのメカニズムを解明することで、同じような条件になりそうな時にあらかじめ警戒を呼び掛けるといったことができる可能性があります。またコンピュータシミュレーションでそうした異常気象が再現できるようになると、長期的な異常気象の予報にも役立てることができるようになるかもしれないということでした。
とはいえ、いまのところ、まだそれは研究途上。現時点でどう異常気象に備えるか、について中三川さんは、とにかく気象庁のウェブサイトを参考にしてほしいということでした。スマホでもパソコンでも「気象庁」カタカナの「キキクル」で検索してみてください。出てくる地図をクリックして、自分の住んでいる場所を探すと、危険度が色別で一目でわかるようになっています。(黄色、赤、紫、黒と事態が深刻になっていきます)
河川氾濫の危険度の「洪水キキクル」と、土砂災害危険度をあらわす「土砂キキクル」、道路や家屋など浸水の危険度をあらわす「浸水キキクル」の3種類があります。
気象庁のホームページ、昔は堅苦しい感じだったのですが、いつのまにかとても使いやすくなっていることを、教えていただきました。
カフェの後半では、こうしたデジタル情報だけでなく、アナログの情報伝達も大事だという話になりました。
これは中三川さんご自身の体験談なのですが、東京都内にお住まいの中三川のお姉さんとお兄さんのうち、2019年の台風19号=東日本台風の時に、お姉さんだけがいち早く避難されたそうです。その理由は、お姉さんが、近所にあった想定浸水深を示す看板を見て、近くの川が氾濫するとどれくらい水が押し寄せてくるかということを実感していたからなのだそうです。そして、避難していなかったお兄さんを電話で説得して避難してもらったとのことでした。
気象庁でデジタル情報の解析をしている中三川さんのお姉さんとお兄さんが、道端の「看板」や「身内の呼びかけ」といったアナログ情報がきっかけで避難行動を決めたというのも面白い話です。
確かに過去の水害では、自治体の首長さんが防災無線の放送で直接住民に避難を呼びかけたことで「ただごとではない」というメッセージがうまく伝わり、多くの方が避難したという事例もあるそうで、普段から災害にあまり関心を持っていない人に早めの避難をしてもらうためには、デジタルアナログを組み合わせた、いろんな工夫が必要だという話になりました。
今回も、会場とオンラインあわせて175人の方にご参加いただきました。中三川さん、参加者のみなさん、ありがとうございました。
※中三川さんは、2023年4月現在、気象庁大気海洋部気候情報課長をされています。



→ポスター(PDF)
→過去のげんさいカフェの様子はこちら