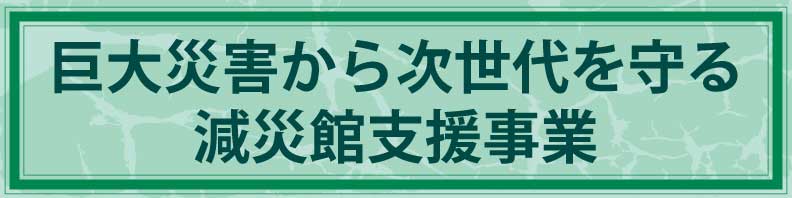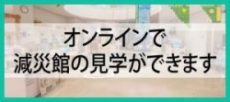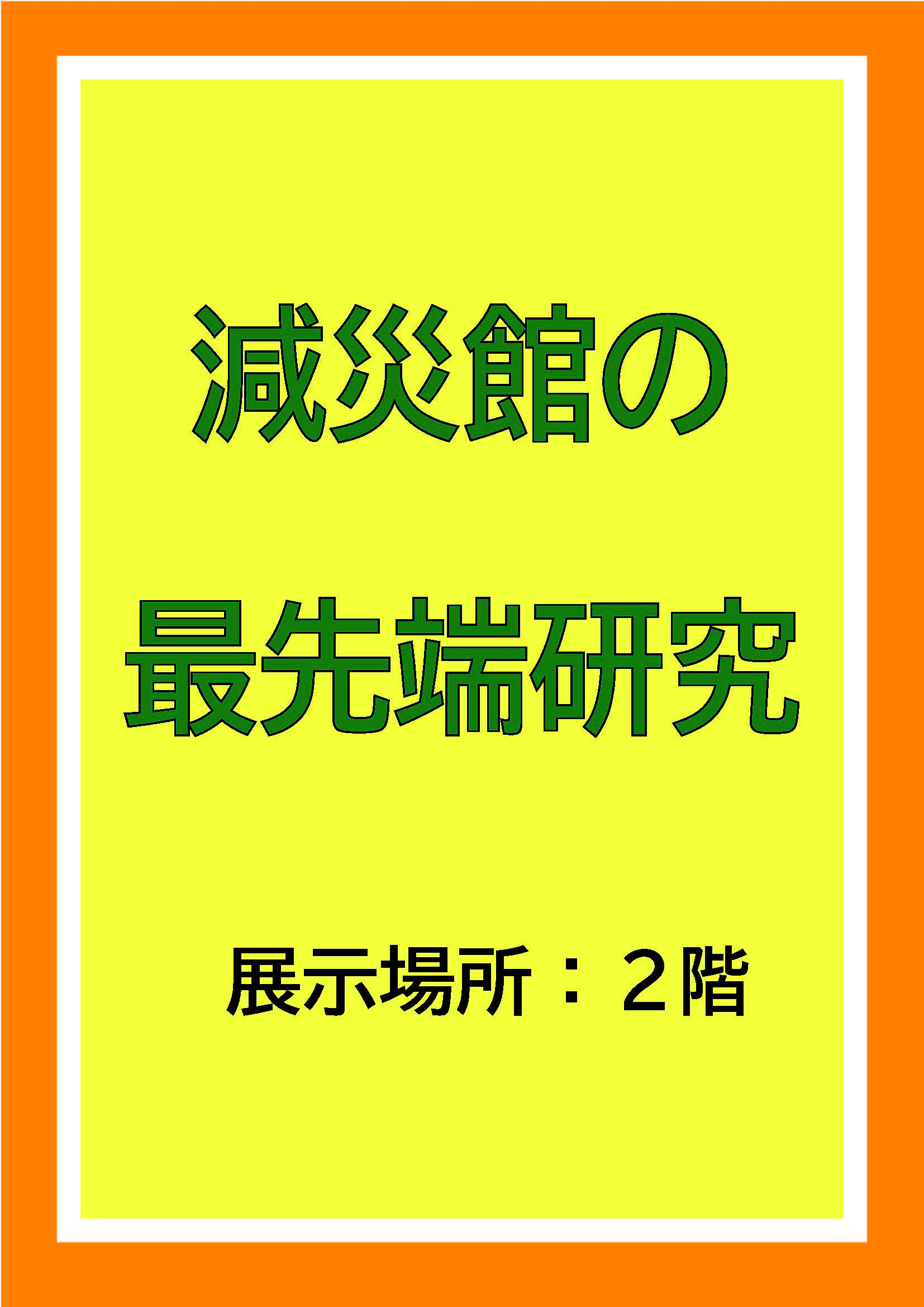地球は内部に蓄えられた熱エネルギーで自ら激しく運動しているダイナミックな星です。その表面では、年間数cmというゆっくりした速度でプレート運動が起きています。この動きが100年、1000年といった長期間続くことで巨大なエネルギーが蓄積され、大地震を引き起こします。大地震の発生間隔が我々の一生と比べて大変長いため、我々は地震のことを忘れやすく、対策を難しくしています。私はこれまで、測地学的手法で地殻変動を調べることで大地震の準備過程および発生過程を研究してきました。今後はこれまでの研究をベースに長期および短期の地震発生予測や地震発生ポテンシャル評価の手法開発を進めていきたいと考えています。名古屋は近い将来大地震の発生が懸念される南海トラフに近いだけでなく、陸側にも多くの活断層があり、地震への備えは大変重要ですが、ただ無闇に地震の恐怖を述べ立てるのではなく、自然科学の知見を広め、人間社会と自然の間の橋渡しすることで、減災に貢献していきたいと考えています。
プレートテクトニクスが隆盛を極める時代に育ち、活断層の動きが地形を作るダイナミックな姿に魅了され、地理学・変動地形学の立場から、これを研究対象としてきました。しかし阪神・淡路大震災で衝撃を受け、防災との関連なくして活断層研究はないと気づき、活断層地図の作成や地震予測の研究と、その成果のわかりやすい説明に心がけてきました。「低頻度巨大災害に如何に備えるか」は難しい課題です。東日本大震災はそのことの深刻さを痛感させ、日本の風土に関する理解に基づく災害観を醸成し、具体的行動に移すことが重要と考えさせられました。経済効率優先の社会から、人命を最優先に考えられる社会への「世直し」も必要なようです。国難による岐路に立つ今日、肩の力を抜いて、本来の日本のあるべき姿を考え直したいと思います。・・著書に、「活断層大地震に備える」(ちくま新書)、「活断層写真判読」(古今書院)など。・・・また、日本活断層学会事務局長として、様々な企画を進めています。 https://jsaf.info/
建築構造学、地震工学、特に振動観測やモニタリングを専門としています。1996年に本学に着任してからは、社会と大学の実際的な建築・都市の課題や防災分野の活動にも取り組んできました。2003年から名古屋大学災害対策室に所属し、2011年からは室長として、名古屋大学の防災体制や防災安全を担当して、2万数千人の組織の防災体制整備、最先端の教育・研究の機能維持、近隣大学や地域社会との連携、そして一人一人の防災力向上と意識啓発に努めてきました。専門分野では、免震建物である減災館の建設に設計段階から関与し、多様な振動実験等を通して免震構造の詳細な特性の把握を進めています。また多様な建築物の振動計測や地域の地震観測に取り組み、災害情報としての建物・地域・社会モニタリングへの展開を目指しています。さらに減災連携研究センターとして、メンバーの多様性と幅広い連携体制を活かした研究活動の推進に取り組んでいきたいと考えています。
名古屋大学工学部で教育・研究に携わった後、運輸省港湾技術研究所(現在の国立研究開発法人海上・港湾・航空技術研究所 港湾空港技術研究所)において長周期波、越波、高潮、津波などの現象およびそれらによる災害の軽減対策に関する研究に関わり、そして名古屋大学大学院環境学研究科に再び着任して主に津波・高潮防災、国土デザインに関する教育・研究に携わり、2022年4月に減災連携研究センターのメンバーになりました。2004年インド洋津波、2011年東日本大震災など国内外10以上の津波や高潮の災害調査を実施し、まちを破壊してしまう自然の力を目の当たりにしてきました。物流、エネルギー生産など生活や経済を支える活動が行われ、豊かなアメニティ空間でもある臨海部は津波や高潮などに襲われる可能性があります。そのような地域における持続性と防災に関する研究を多くの人との連携により進め、災害に強い魅力ある地域づくりに貢献したいと考えています。
博士研究員として米国大学を含む複数の大学に所属し、鉄筋コンクリート造建物、鋼構造建物、基礎構造に関する耐震工学研究に取り組みました。その後、独立行政法人防災科学技術研究所兵庫耐震工学研究センターにおいて、E-Defense(実大三次元震動破壊実験施設)に基づく超高層建物の調査開発研究(兵庫共同プロジェクト、文部科学省プロジェクト)、高耐震コンクリート系建物の調査開発研究(日米共同プロジェクト)に従事しました。南海トラフ巨大地震が太平洋ベルト地帯を広域に襲うと予測されています。人命の安全、生活基盤の維持の点から、建築物の耐震性向上は地震防災の基本です。近年になり、巨大地震時における長周期地震動の特徴が明らかとなっています。超高層建物に対して、新たな情報を反映した再評価と適切な耐震対策が必要です。一般建物群については、施工性、経済性に優れた普及力の高い高耐震構法の開発と設計法の構築が新たな進展をもたらします。こうした耐震工学を基盤とする重要課題に、研究分野間連携、社会連携、国際連携等を通じて、精力的に取り組んで行きます。
人と防災未来センター、京都大学大学院、国立環境研究所で、市民の安全・安心を確保するため、計画論からみた水道事業体の危機管理対策、市民の視点を組み込んだ上水道システムの災害対策やリスクコミュニケーション手法、災害廃棄物対策やマネジメント手法などの研究に携わってきた後、2016年4月に本学減災連携研究センターに着任しました。災害と環境の視点から、災害時の人命・健康・環境に対する影響を低減するための社会システムをデザイン・管理するための技法に関する体系に取り組み、災害と環境に関する減災のための「知」を探究します。「持続可能な社会」が、災害時においても「安全・安心な社会」であるという仮説のもと、産官学民や地域との階層的連携による実践的な災害環境や防災・減災学の研究教育を行い、名古屋をはじめ、東海地域や中部圏の減災連携の確立に貢献できるよう、頑張ります。
神戸大学工学部建築学科で、阪神・淡路大震災で被災しながらも地域の支援にあたった先生方の話を聞き、災害レジリエンスに向けた取り組みについて関心を持ちました。さらに、在学中に東日本大震災が発生し、災害の悲惨さと防災・減災の大切さを痛感しました。2017年神戸大学大学院工学研究科建築学専攻博士課程後期課程を修了後、神戸大学都市安全研究センター、人と防災未来センターで勤務しました。これまで、<建築×福祉×防災>をテーマに災害時要配慮者の避難行動や避難生活の安全・安心について研究するとともに、大阪府北部地震や平成30年7月豪雨(西日本豪雨)等における被災自治体への支援活動、自治体防災職員向けの研修開発等を行なってきました。自治体や地域の皆様に寄り添いながら課題を共に解決し縮災を実現できるよう、貢献していきたいと考えています。どうぞよろしくお願いいたします。
名古屋大学大学院環境学研究科で都市計画・まちづくり分野を学び、2014年に名古屋大学減災連携研究センターの研究員に着任、2023年より現職。専門は都市計画、防災まちづくり。大規模災害に備え、事前復興・事前準備の視点から、市民・企業・行政・専門家が垣根を越えて議論することが
大切だと思っております。とくに、災害対応における自治体間の連携や組織間連携・部局内の連携の重要性に着目しています。その為の議論の場づくりと、GIS等を用いた情報共有や状況認識の統一に基づく、ワークショップ形式を主体とする検討過程の整理と議論の枠組みのあり方について研究を進め、地域の防災・減災力の向上に皆さまと一緒に取組んで参りたいと思います。
大切だと思っております。とくに、災害対応における自治体間の連携や組織間連携・部局内の連携の重要性に着目しています。その為の議論の場づくりと、GIS等を用いた情報共有や状況認識の統一に基づく、ワークショップ形式を主体とする検討過程の整理と議論の枠組みのあり方について研究を進め、地域の防災・減災力の向上に皆さまと一緒に取組んで参りたいと思います。