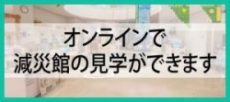災害時の水を確保するには
(減災館第27回特別企画展「埋設管路」との連携企画)
ゲスト:災害環境工学者 平山 修久さん
(名古屋大学減災連携研究センター准教授)
日時:2019年7月8日(月)18:00〜19:30
場所:名古屋大学減災館1階減災ギャラリー
企画・ファシリテータ: 隈本 邦彦
(江戸川大学教授/名古屋大学減災連携研究センター客員教授)

水道の蛇口をひねればいつでもきれいな水が出てくる。ふだんこれが当たり前のことのように感じている私たちですが、いざ大災害のときには、そのことがいかに有り難いことだったのか身にしみてわかります。
「被災地で起きる断水」が今回のカフェのテーマです。7月17日から始まる減災館特別企画展「暮らしを支える埋設管路」の連携企画として、監修をされた平山さんにゲストに来ていただきました。被災地の断水をいかに未然に防ぐか、また起きてしまった場合は、いかにそれを早く復旧させるかを研究している研究者の一人です。
平山さんによると、日本の水道は、過去の災害から教訓を学んで強くなってきたという歴史があるそうです。
1978年の宮城県沖地震からは、水道の配水区域を適切な広さに分けて管理するブロック化の大切さが、1995年の阪神・淡路大震災からは管路を耐震化しておくことの重要性が、そして2007年新潟県中越沖地震では応急給水システムの改善の必要性等が明らかになり、それぞれがいまの水道の災害対策に取り入れられてきているそうです。
ところが、去年の西日本豪雨では、新たな問題点が浮き彫りになりました。
そもそも水道は、エンドユーザー側に近い「給水管」や「配水管」の被害であれば、比較的短期間に復旧することが可能です。しかしシステムのより上流側にあたる「浄水場」や「取水場」等が被災すると、断水が大規模になり、さらに復旧までに多くの期間がかかってしまうことになりがちです。
最大26万戸余が断水した西日本豪雨では、岡山県、広島県、愛媛県で上流側の「浄水場」や「取水場」が土砂流入や冠水などの大きな被害を受け、被災地での断水が大規模化し、復旧が遅れました。中でも愛媛県宇和島市の吉田浄水場は7月7日の豪雨で大量の土砂や流木が流れ込み壊滅的な被害を受けました。これにより長期の断水がおきる恐れがあったため、急きょ川の下流に仮設の浄水施設を突貫工事で作って対応したということでした。
こうした経験を教訓に、平山さんたちは、各都道府県の大雨の被害想定と主要な水道施設の所在地を重ね合わせることで、全国の水道施設がどの程度水害のリスクにさらされているかを改めて調査しました。
その結果、施設数で全体の10%にあたる990施設が「浸水想定」地域に入っており、10.5%にあたる1047施設が「土砂災害警戒区域」に入っていたことがわかったそうです。
西日本豪雨のような記録的な大雨が降った時には、これらの地域は大規模な断水に見舞われるリスクがあるということになります。
これからの水道は、従来の地震対策だけでなく、地域特性を考慮した水害対策も必要だということですね。
会場には、カフェの話題にも出てきた宇和島市吉田浄水場の被害の復旧に貢献したという岐阜県の会社の方も来られていて、その会社が無償で提供した仮設タンクは、なんと熊本地震の被災地で使われた後、「また何かあるかもしれない」と念のため解体せずに会社の敷地に保管されていたものだった、という秘話が明かされました。そのおかげで現地の水道の復旧はかなり早まったそうで、善意がそんな形で生かされたのだそうです。
平山さん、会場の皆さん、今回もありがとうございました。